立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
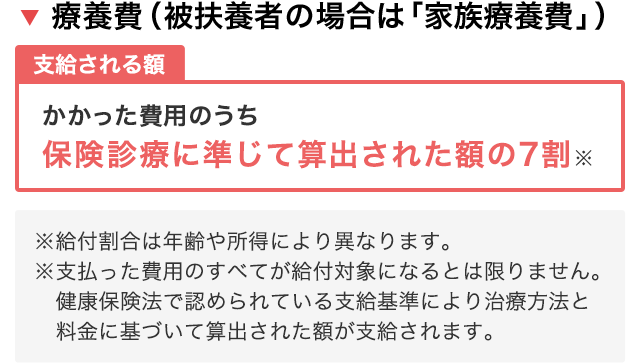
旅先で急病になったときなど、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。
- ※医療機関によっては、自費診療(10割負担)の場合、消費税を加算されることがありますが、療養費は、消費税を除いて算出します。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
健康保険では、次のような場合も「療養費」が支給されます。
| 療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
|---|---|
| 生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
| 保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
| 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき※ | 基準料金の7割 |
| 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを医師の指示により作成・購入したとき <上限額>眼鏡:40,492円 コンタクトレンズ:13,780円 |
上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
|
上限の範囲内の7割 |
| スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
※払い戻しを受けられるのは以下の場合に限られています
- はり、きゅうの施術を受けたとき
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等の慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、施術により相当の効果があるとして医師が同意したとき。
なお、同一疾患で医療機関を受診している期間は、はり、きゅう代金を払い戻し請求をすることはできません。 - マッサージの施術を受けたとき
筋麻痺、関節拘縮などで、施術により相当の効果があるとして医師が同意したとき。
海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- ※実際に現地で支払った額の方が算定された額より低いときは、その実費額が給付の対象になります。
- 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、領収書(原本)、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写しの添付が必要になります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
入転院で移送が必要なとき
移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やけがにより移動することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師の指示により、一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
支給要件
移送費の支給は、当健保組合が以下の3点のいずれにも該当すると認めた場合に行われます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
したがって、通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません。
移送費が支給される標準的な事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
移送費の支給額
移送費の額は、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の費用にもとづき算定した額の範囲内での実費となります。
具体的には、患者の状態に応じて、①必要な医療を行いうる最寄りの医療機関まで最も経済的な経路で、②最も経済的な交通機関の運賃を算定します。
医師などの付添人については、医師が医学的管理の必要があると判断した場合に限り、原則として1人分の交通費を算定することができます。





